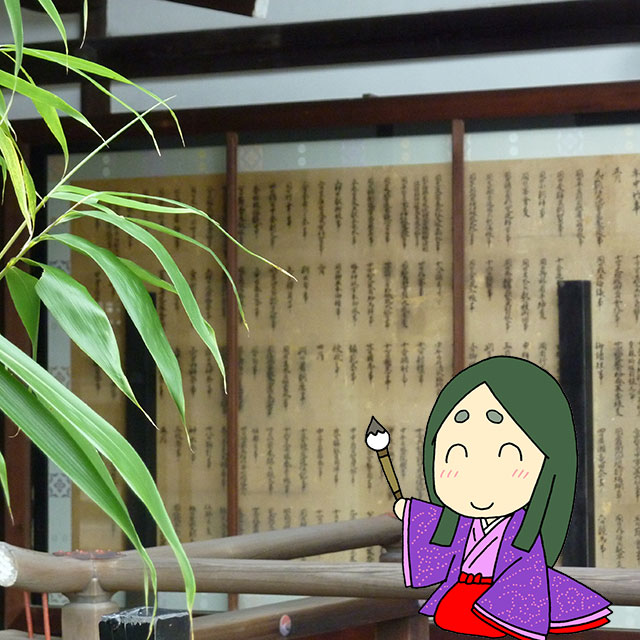更級日記原典(物語に没頭)
6.梅の立枝(寛仁四年-治安元年)
ひろびろと荒れたる所の、過ぎ來つる山々にもおとらず、大きに恐しげなるみ山木どものやうにて、都の内とも見えぬ所のさまなり。ありもつかず、いみじうものさわがしけれども、いつしかと思ひし事なれば、「物語もとめて見せよ、見せよ」と母をせむれば、三條の宮に、親族なる人の衞門の命婦とてさぶらひけるたづねて、文やりたれば、珍しがりて、喜びて、御前のをおろしたるとて、わざとめでたき草子ども、硯の箱の蓋に入れておこせたり。嬉しくいみじくて、夜晝これを見るよりうち始め、又々も見まほしきに、ありもつかぬ都のほとりに、誰かは物語もとめ見する人のあらむ。
繼母なりし人は、宮仕へせしが下りしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世中うらめしげにて、外にわたるとて、五つばかりなる乳兒どもなどして、「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」などいひて、梅の木の、つま近くて、いと大きなるを、「これが花の咲かむ折は來むよ」といひおきてわたりぬるを、心のうちに戀しくあはれなりと思ひつゝ、しのび音をのみ泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、來むとありしを、さやあると、目をかけて待ちわたるに、花もみな咲きぬれど、おともせず、思ひわびて、花を折りてやる。
たのめしをなほや待つべき霜枯れし梅をも春はわすれざりけり といひやりたれば、あはれなることども書きて、 なほたのめ梅の立ち枝はちぎりおかぬ思ひのほかの人も訪ふなり その春、世の中いみじうさわがしうて、まつさとのわたりの月かげあはれに見し乳母も、三月朔日になくなりぬ。せむ方なく思ひ歎くに、物語のゆかしさもおぼえずなりぬ。いみじく泣きくらして見いだしたれば、夕日のいと花やかにさしたるに、櫻の花残りなく散りみだる。
散る花も又來む春は見もやせむやがて別れし人ぞこひしき
又きけば、侍從の大納言の御むすめなくなり給ひぬなり。殿の中將のおぼし歎くなるさま、わがものの悲しき折なれば、いみじくあはれなりと聞く。上り着きたりし時、「これ手本にせよ」とて、この姫君の御手をとらせたりしを、「さ夜ふけてねざめざりせば」など書きて、 「鳥邊山谷に煙の燃えたゝばはかなく見えし我と知らなむ」と、いひ知らずをかしげに、めでたく書き給へるを見て、いとゞ涙を添へまさる。
7 物語(治安元年-同二年)
かくのみ思ひくんじたるを、心も慰めむと、心ぐるしがりて、母、物語などもとめて見せ給ふに、げに、おのづから慰みゆく。紫のゆかりを見て、つゞきの見まほしくおぼゆれど、人かたらひなどもえせず。誰もいまだ都なれぬほどにて、え見つけず。いみじく心もとなく、ゆかしくおぼゆるまゝに、「この源氏の物語、一の卷よりしてみな見せ給へ」と心の内に祈る。親の太秦に籠り給へるにも、こと事なく、この事を申して、いでむまゝにこの物語見はてむと思へど、見えず。いと口惜しく思ひ歎かるゝに、をばなる人のゐなかよりのぼりたる所にわたいたれば、「いとうつくしう、生ひなりにけり」など、あはれがり、めづらしがりて、歸るに、「何をか奉らむ、まめまめしき物は、まさなかりなむ、ゆかしくし給ふなる物を奉らむ」とて、源氏の五十餘卷、櫃に入りながら、ざい中將、とほぎみ、せり河、しらゝ、あさうづなどいふ物語ども、一袋とり入れて、得て歸る心地の嬉しさぞいみじきや。はしるはしる、わづかに見つゝ、心も得ず心もとなく思ふ源氏を、一の卷よりして、人もまじらず、几帳の内にうち臥してひき出でつゝ見る心地、后の位も何にかはせむ。晝は日ぐらし、夜は目のさめたるかぎり、火を近くともして、これを見るよりほかの事なければ、おのづからなどは、空におぼえ浮かぶを、いみじきことに思ふに、夢にいと清げなる僧の、黄なる地の袈裟着たるが來て、「法華經五卷をとくならへ」といふと見れど、人にも語らず、習はむとも思ひかけず、物語の事をのみ心にしめて、われはこの頃わろきぞかし、盛りにならば、容貌もかぎりなくよく、髪もいみじく長くなりなむ。光るの源氏の夕顔、宇治の大將の浮舟の女君のやうにこそあらめと思ひける心、まづいとはかなくあさまし。 五月ついたちごろ、つま近き花橘の、いと白く散りたるをながめて、
時ならずふる雪かとぞながめまし花橘のかをらざりせば
足柄といひし山の麓に、暗がりわたりたりし木のやうに、しげれる所なれば、十月ばかりの紅葉、四方の山邊よりもけに、いみじくおもしろく、錦をひけるやうなるに、ほかより夾たる人の、「今、まゐりつる道に紅葉のいとおもしろき所のありつる」といふに、ふと、
いづこにもおとらじものをわが宿の世を秋はつる景色ばかりは
物語の事を、晝はひぐらし思ひつゞけ、夜も目のさめたるかぎりは、これをのみ心にかけたるに、夢に見ゆるやう、「このごろ皇太后宮の一品の宮の御料に、六角堂に遣水をなむ作るといふ人あるを、『そはいかに』と問へば、『天照御神を念じませ』といふ」と見て、人にもかたらず、何とも思はでやみぬる、いといふかひなし。春ごとに、この一品の宮をながめやりつゝ、
咲くと待ち散りぬとなげく春はたゞわが宿がほに花を見るかな
三月つごもりがた、土忌に人のもとに渡りたるに、櫻さかりにおもしろく、今まで散らぬもあり。かへりて又の日、 あかざりし宿の櫻を春くれて散りがたにしも一目見しかな
といひにやる。
8.大納言殿の姫君(治安二年-同三年)
花の咲き散る折ごとに、乳母なくなりし折ぞかしとのみあはれなるに、おなじ折なくなり給ひし侍從大納言の御女の手を見つゝ、すゞろにあはれなるに、五月ばかりに、夜更くるまで、物語をよみて起きゐたれば、來つらむ方も見えぬに、猫のいとなごうないたるを、驚きて見れば、いみじうをかしげなる猫あり。いづくより來つる猫ぞと見るに、姉なる人、「あなかま、人に聞かすな。いとをかしげなる猫なり。飼はむ」とあるに、いみじう人なれつゝ、傍にうちふしたり。尋ぬる人やあると、これを隱して飼ふに、すべて下衆のあたりにもよらず、つと前にのみありて、物もきたなげなるは、ほかざまに顔をむけて食はず。姉おとゝの中につとまとはれて、をかしがりらうたがるほどに、姉のなやむことあるに、ものさわがしくて、この猫を北面にのみあらせて呼ばねば、かしがましくなきのゝしれども、なほさるにてこそはと思ひてあるに、煩ふ姉おどろきて、「いづら、猫は。こちゐて夾」とあるを、「など」と問へば、「夢にこの猫の傍に來て、『おのれは、侍從の大納言殿の御女のかくなりたるなり。さるべき縁のいさゝかありて、この中の君のすゞろにあはれと思ひいで給へば、たゞしばしこゝにあるを、このごろ下衆の中にありて、いみじうわびしきこと』といひて、いみじうなく様は、あてにをかしげなる人と見えて、うち驚きたれば、この猫の聲にてありつるが、いみじくあはれなるなり」と語り給ふを聞くに、いみじくあはれなり。その後は、この猫を北面にもいださず、思ひかしづく。ただひとりゐたる所に、この猫がむかひゐたれば、かいなでつゝ、「侍從大納言の姫君のおはするな。大納言殿にしらせ奉らばや」といひかくれば、顔をうちまもりつゝ、なごうなくも、心のなし、目のうちつけに、例の猫にはあらず、聞き知り顔にあはれなり。
世の中に長恨歌といふ文を、物語に書きてある所あんなりと聞くに、いみじくゆかしけれど、えいひよらぬに、さるべきたよりをたづねて、七月七日いひやる。
ちぎけむ昔の今日のゆかしさにあまの河浪うち出でつるかな
返し、 たち出づる天の河邊のゆかしさに常はゆゆしきことも忘れぬ
その十三日の夜、月いみじく隈なくあかきに、皆人も寢たる夜中ばかりに、縁に出でゐて、姉なる人、そらをつくづくと眺めて、「たゞ今ゆくへなく飛び失せなばいかゞ思ふべき」と問ふに、なまおそろしと思へるけしきを見て、こと事にいひなして笑ひなどして聞けば、かたはらなる所に、さき追ふ車とまりて、「荻の葉荻の葉」と呼ばすれど、答へざなり。呼びわづらひて、笛をいとをかしく吹き澄まして、過ぎぬなり。
笛のねのたゞ秋風と聞ゆるになど荻の葉のそよと答へぬ といひたれば、げにとて、
荻の葉の答ふるまでも吹きよらでたゞに過ぎぬる笛の音ぞ憂き かやうにあくるまで眺めあかいて、夜あけてぞ皆人寢ぬる。
そのかへる年、四月の夜中ばかりに火の事ありて、大納言殿の姫君と思ひかしづきし猫も燒けぬ。「大納言殿の姫君」と呼びしかば、聞き知り顔になきて、歩み來などせしかば、父なりし人も、「めづらかにあはれなることなり。大納言に申さむ」などありしほどに、いみじうあはれに、くちおしくおぼゆ。
9 野邊の笹原(萬壽元年-同二年)
広々と物ふかきみ山のやうにはありながら、花紅葉の折は、四方の山邊も何ならぬを見ならひたるに、たとしへなくせばき所の、庭のほどもなく、木なども無きに、いと心憂きに、むかひなる所に、梅、紅梅など咲きみだれて、風につけて、かかえ來るにつけても、住みなれしふるさとかぎりなく思ひ出でらる。
にほひくる隣の風を身にしめてありし軒端の梅ぞこひしき
その五月の朔日に、姉なる人、子うみてなくなりぬ。よそのことだに、をさなくよりいみじくあはれとおもひわたるに、ましていはむ方なく、あはれかなしと思ひ歎かる。母などはみはなくなりたる方にあるに、形見にとまりたるをさなき人々を左右に臥せたるに、荒れたる板屋の隙より月の洩り來て、ちごの顔にあたりたるが、いとゆゝしくおぼゆれば、袖を打ちおほひて、いま一人をもかき寄せて、思ふぞいみじきや。 そのほど過ぎて、親族なる人のもとより、「昔の人のかならず求めておこせよとありしかば、求めしに、その折はえ見出でずなりにしを、今しも人のおこせたるが、あはれに悲しきこと」とて、かばね尋ぬる宮といふ物語をおこせたり。まことにぞあはれなるや。返りごとに、
うづもれぬかばねを何に尋ねけむ苔のしたには身こそなりけれ
乳母なりし人、「いまは何につけてか」など、泣く泣くもとありける所に歸りわたるに、
「故郷にかくこそ人は歸りけれあはれいかなる別れなりけむ 昔のかたみには、いかでとなむ思ふ」など書きて、「硯の水の氷れば、みなとぢられてとゞめつ」といひたるに、
かき流すあとはつらゝにとぢてけり何を忘れぬ形見とか見む
といひやりたる返りごとに、
なぐさむる方もなぎさの濱千鳥なにか憂き世にあともとゞめむ
この乳母、墓所見て、泣く泣く歸りたりし、
のぼりけむ野べは煙もなかりけむいづこをはかと尋ねてか見し
これを聞きて繼母なりし人、
そこはかと知りてゆかねど先に立つ涙ぞ道のしるべなりける
かばねたづぬる宮おこせたりし人、
すみなれぬ野べの笹原あとはかもなくなくいかに尋ねわびけむ
これを見て、せうとは、その夜おくりに行きたりしかば、
見しまゝに燃えし煙はつきにしをいかゞ尋ねし野べの笹原
雪の日をへて降るころ、吉野山に住む尼君を思ひやる。
雪ふりてまれの人めも絶えぬらむ吉野の山の峯のかけ道
かへる年、睦月の司召に、親のよろこびすべきことありしに、かひなきつとめて、同じ心に思ふべき人のもとより、「さりともと思ひつゝ、あくるを待ちつる心もとなさ」といひて、
あくる待つ鐘のこゑにも夢さめて秋のもゝ夜の心地せしかな といひたる返りごとに、
暁をなにに待ちけむ思ふ事なるともきかぬ鐘のおとゆゑ
10.東山なる所(萬壽二年-同三年)
四月つごもりがた、さるべきゆゑありて、東山なる所へうつろふ。道のほど、田の、苗代水まかせたるも、植ゑたるも、何となく青み、をかしう見えわたりたる。山のかげくらう、前ちかう見えて、心ぼそくあはれなるゆふぐれ、水鷄いみじくなく。
たゝくとも誰かくひなの暮れぬるに山路をふかくたづねては來む
靈山ちかき所なれば、詣でてをがみ奉るに、いと苦しければ、山寺なる石井によりて、手にむすびつゝ飮みて、「この水の飽かずおぼゆるかな」といふ人のあるに、
奥山の石間の水をむすびあげてあかぬものとは今のみやしる といひたれば、水飮む人、
山の井のしづくに濁る水よりもこはなほあかぬ心地こそすれ
歸りて、夕日けざやかにさしたるに、宮この方も殘りなく見やらるゝに、このしづくに濁る人は、京に歸るとて、心苦しげに思ひて、またつとめて、
山の端に入日のかげは入りはてて心ぼそくぞながめやられし
念佛する僧の曉に額づく音の尊く聞ゆれば、戸をおし開けたれば、ほのぼのあけゆく山ぎは、こぐらき梢どもきりわたりて、花紅葉の盛りよりも、なにとなく、茂りわたれる空のけしき、曇らはしくをかしきに、郭公さへ、いと近き梢にあまた度鳴いたり。
誰に見せ誰に聞かせむ山里のこの曉もをちかへる音も このつごもりの日、谷の方なる木の上に、郭公、かしがましく鳴いたり。
都には待つらむ物を郭公けふ日ねもすに鳴きくらすかな
などのみ、ながめつゝ、もろともにある人、「ただいま、京にも聞きたらむ人あらむや。かくてながむらむと思ひおこする人あらむや」などいひて、
山深く誰か思ひはおこすべき月見る人は多からめども といへば、
ふかき夜に月見る折は知らねどもまづ山里ぞ思ひやらるゝ
曉になりやしぬらむと思ふほどに、山の方より人あまた來る音す。驚きて見やりたれば、鹿の縁のもとまで來てうちないたる、ちかうてはなつかしからぬものゝ聲なり。
秋の夜のつま戀ひかぬる鹿のねはとほ山にこそきくべかりけれ
しりたる人の近きほどに來て歸りぬと聞くに、
まだ人め知らぬ山邊の松風もおとしてかへるものとこそ聞け
八月になりて、廿よ日の曉がたの月、いみじくあはれに、山の方はこ暗く、瀧の音も似る物なくのみ眺められて、
思ひ知る人に見せばや山里の秋の夜ふかき有明の月
京にかへり出づるに、わたりし時は水ばかり見えし田どもも、みな刈りはててけり。
苗代の水かげばかり見えし田の刈りはつるまでなが居しにけり
十月つごもりがたに、あからさまに來て見れば、こ暗う繁れし木の葉ども殘りなく散りみだれて、いみじくあはれげに見えわたりて、心ちよげにさゝらぎ流れし水も木の葉に埋もれて、あとばかり見ゆ。
水さへぞすみ絶えにける木の葉ちる嵐の山の心ぼそさに
そこなる尼に、「春まで命あらばかならずこむ。花ざかりはまづ告げよ」などいひて歸りにしを、年かへりて三月十餘日になるまでおともせねば、
契りおきし花の盛りを告げぬかな春やまだ來ぬ花やにほはぬ
旅なる所に來て、月のころ、竹のもと近くて、風の音に目のみ覺めて、うちとけて寢られぬころ、
竹の葉のそよぐ夜ごとに寢ざめしてなにともなきに物ぞ悲しき
秋ごろ、そこをたちて、ほかへうつろひて、そのあるじに、
いづことも露のあはれはわかれじを淺茅が原の秋ぞ戀しき
11 子忍びの森(-長元五年)
繼母なりし人、下りし國の名を宮にもいはるゝに、異人通はして後も、なほその名をいはるときゝて、親の今はあいなきよし、いひにやらむ、とあるに、
朝倉や今は雲井に聞く物をなほ木のまろが名のりをやする
かやうに、そこはかとなきことを思ひつゞくるを役にて、物詣をわづかにしても、はかばかしく、人のやうならむとも念ぜられず、このころの世の人は十七八よりこそ經よみ、おこなひもすれ、さること思ひかけられず。からうじて思ひよることは、いみじくやむごとなく、かたちありさま、物語にある光る源氏などのやうにおはせむ人を、年に一たびにても通はし奉りて、浮舟の女君のやうに、山里に隠しすゑられて、花、紅葉、月、雪を眺めて、いと心細げにて、めでたからむ御文などを、時々待ち見などこそせめとばかり思ひつゞけ、あらまし事にもおぼえけり。
おや、となりなば、いみじうやむごとなくわが身もなりなむなど、たゞゆくへなき事をうち思ひ過すに、親、からうじて、はるかにとほきあづまになりて、「年ごろは、いつしか思ふやうに近き所になりたらば、まづ胸あくばかりかしづきたてて、ゐて下りて、海山の景色も見せ、それをばさる物にて、わが身よりも高うもてなしかしづきて見むとこそ思ひつれ、我も人も宿世のつたなかりければ、ありありてかくはるかなる國になりにたり。をさなかりし時、あづまの國にゐて下りてだに、心地もいさゝかあしければ、これをや、この國に見すてて、迷はむとすらむと思ふ。人の國の恐しきにつけても、わが身一つならば、安らかならましを、ところせう引き具して、いはまほしきこともえいはず、せまほしきこともえせずなどあるが、わびしうもあるかなと心を砕きしに、今はまいて大人になりにたるを、ゐて下りて、わが命も知らず、京のうちにてさすらへむは例のこと、あづまの國、田舍人になりて迷はむ、いみじかるべし。京とても、たのもしう迎へとりてむと思ふ類、親族もなし。さりとて、わづかになりたる國を辭し申すべきにもあらねば、京にとゞめて、ながきわかれにてやみぬべきなり。京にも、さるべきさまにもてなしてとゞめむとは思ひよる事にもあらず」と夜晝なげかるゝを聞く心地、花紅葉の思ひもみな忘れて悲しく、いみじく思ひ歎かるれど、いかゞはせむ。
七月十三日にくだる。五日かねては見むもなかなかなべければ、内にも入らず。まいてその日は立ちさわぎて、時なりぬれば、今はとてすだれを引きあげて、うち見合はせて涙をほろほろと落して、やがて出でぬるを見おくる心地、目もくれまどひて、やがて臥されぬるに、とまる男のおくりして歸るに、懷紙に、
思ふ事心にかなふ身なりせば秋の別れを深く知らまし とばかり書かれたるをも、え見やられず、事よろしき時こそ腰折れかゝりたる事も思ひつゞけけれ、ともかくもいふべき方もおぼえぬまゝに、
かけてこそ思はざりしかこの世にてしばしも君に別るべしとは とや書かれにけむ。
いとゞ人目も見えず、さびしく心細くうちながめつゝ、いづこばかりと、あけくれ思ひやる。道のほども知りにしかば、はるかに戀しく心細きことかぎりなし。あくるより暮るゝまで、東の山ぎはを眺めて過ぐす。
八月ばかりに太秦にこもるに、一條より詣づる道に、をとこ車ふたつばかりひきたてて、物へ行くに、もろともに夾べき人待つなるべし。過ぎて行くに、隨身だつ者をおこせて、
花見にゆくときみを見るかな といはせたれば、かかるほどの事はいらへぬも便なしなどあれば、
千ぐさなる心ならひに秋の野の とばかりいはせて行き過ぎぬ。
七日さぶらふほども、たゞ東路のみ思ひやられてよしなし。「こと、からうじて離れて、たひらかにあひ見せ給へ」と申すは、佛もあはれと聞き入れさせ給ひけむかし。
冬になりて、日ぐらし雨降り暮らいたる夜、くもかへる風はげしううちふきて、空晴れて月いみじうあかうなりて、軒ちかき荻のいみじく風に吹かれて、碎けまどふが、いとあはれにて、
秋をいかに思ひ出づらむ冬深み嵐にまどふ荻の枯葉は
あづまより人夾たり。 「神拜といふわざして國の内ありきしに、水をかしく流れたる野の、はるばるとあるに、木むらのある、をかしき所かな、見せでと、まづ思ひいでて、こゝはいづことかいふと問へば、子忍びの森となむ申すと答へたりしが、身によそへられて、いみじく悲しかりしかば、馬より下りて、そこにふた時なむながめられし。
とどめおきてわがごと物や思ひけむ見るに悲しき子忍びの森 となむ覺えし」とあるを、見る心地、いへばさらなり。返り事に、
子忍びを聞くにつけてもとゞめおきしちゝぶの山のつらきあづま路
12.鏡のかげ(長元六年-同九年)
かうて、つれづれととながむるに、などか物詣もせざりけむ。母いみじかりし古代の人にて、初瀬には、あなおそろし、奈良坂にて人にとられなばいかゞせむ。石山、關山越えていとおそろし。鞍馬はさる山、ゐていでむ、いと恐ろしや。親上りて、ともかくもと、さし放ちたる人のやうに、わづらはしがりて、わづかに清水にゐて籠りたり。それにも、例の癖は、まことしかべい事も思ひ申されず。彼岸のほどにて、いみじうさわがしう恐ろしきまでおぼえて、うちまどろみ入りたるに、御帳の方のいぬふせぎの内に、青き織物の衣を着て、錦を頭にもかづき、足にも履いたる僧の、別當とおぼしきが寄り來て、「行くさきのあはれならむも知らず、さもよしなし事をのみ」と、うちむづかりて、御帳の内に入りぬと見ても、うちおどろきても、かくなむ見えつるとも語らず、心に思ひとゞめでまかでぬ。
母一尺の鏡を鑄させて、えゐてまゐらぬかはりにとて、僧を出だし立てて初瀬に詣でさすめり。「三日さぶらひて、この人のあべからむさま、夢に見せ給へ」などいひて、詣でさするなめり。そのほどは精進せさす。この僧歸りて、「夢をだに見でまかでなむが本意なきこと、いかゞ歸りても申すべきと、いみじう額づきおこなひて寢たりしかば、御帳の方より、いみじう氣高う清げにおはする女の、うるはしく装束き給へるが、奉りし鏡をひきさげて、『この鏡には、文や添ひたりし』と問ひ給へば、かしこまりて、『文もさぶらはざりき。この鏡をなむたてまつれと侍りし』と答へ奉れば、『あやしかりける事かな。文添ふべきものを』とて、『この鏡を、こなたに寫れる影を見よ、これ見ればあはれに悲しきぞ』とて、さめざめとなき給ふを見れば、ふしまろび泣き歎きたる影寫れり。『この影を見れば、いみじう悲しな。これ見よ』とて、いま片つ方に寫れる影を見せ給へば、御簾どもあをやかに、几帳おし出でたる下より、いろいろの衣こぼれ出で、梅櫻咲きたるに、鶯木傳ひ鳴きたるを見せて、『これを見るは嬉しな』と、のたまふとなむ見えし」と語るなり。いかに見えけるぞとだに、耳もとゞめず。物はかなき心にも、「常に天照御神を念じ申せ」といふ人あり、いづこにおはします、神佛にかはなど、さはいへど、やうやう思ひわかれて、人に問へば、「神におはします。伊勢におはします。紀伊の國に、紀の國造と申すは、この御神なり。さては内侍所に、すべら神となむおはします」といふ。「伊勢の國までは思ひかくべきにもあらざなり。内侍所にも、いかでかはまゐりをがみ奉らむ。空の光を念じ申すべきにこそは」など、浮きておぼゆ。
親族なる人、尼になりて、修學院にいりぬるに、冬ごろ、
涙さへふりはへつゝぞ思ひやる嵐吹くらむ冬の山里
返し、 わけて問ふ心のほどの見ゆるかな木蔭をぐらき夏の茂りを
東に下りし親、からうじて上りて、西山なる所に落ちつきたれば、そこに皆渡りて見るに、いみじう嬉しきに、月のあかき夜一夜物語などして、
かかる世もありける物を限りとて君に別れし秋はいかにぞ といひたれば、いみじく泣きて、
思ふ事かなはずなぞといとひこし命のほども今ぞうれしき
これぞ別れの門出といひ知らせしほどの悲しさよりは、たひらかに待ちつけたるうれしさもかぎりなけれど、「人の上にても見しに、老い衰へて世に出で交らひしは、をこがましく見えしかば、我はかくて閉ぢこもりぬべきぞ」とのみ、殘りなげに世を思ひいふめるに、心細さ堪へず。
東は野のはるばるとあるに、東の山ぎはは、比叡の山よりして、稻荷などいふ山まであらはに見えわたり、南はならびの岡の松風、いと耳近う心細く聞えて、内にはいたゞきのもとまで、田といふものの、ひた引き鳴らす音など、ゐなかの心ちして、いとをかしきに、月のあかき夜などは、いとおもしろきを、ながめ明かし暮らすに、知りたりし人、里とほくなりておともせず。たよりにつけて、「何事かあらむ」と傳ふる人に驚きて、
思ひ出でて人こそとはね山里のまがきの荻に秋風は吹く
といひにやる。