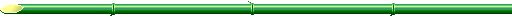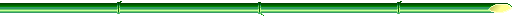継母が離婚後も上総太輔と呼ばせていた訳は?
宮仕えでの女房の呼称
継母は帰京後十年の後まで、既に他の男性と再婚しているというのに、宮仕えの中で自分のことを離婚した孝標の任地にちなんだ上総太輔という名で呼ばせていました。父、孝標はそのことで、同僚から冷やかされることがあったのでしょうか。自分で直接言いにくいものだから、娘に頼んでそれをやめるように歌を代作させています。更級作者は、父のために歌を送ってその意を伝えます(親孝行ですね)。
朝倉やいまは雲井に聞く物をなほ木(こ)のまろが名のりをやする
(今は宮様にお仕えされているというのに、今でも私にちなむ名乗りをされているんですか)
でもこれは全然悪気はないんです。更級の作者ばかりでなく、継母にとっても、上総での生活や東海道の旅はその時は大変でも振り返って見れば、刺激に満ちた楽しい冒険旅行であったのです。彼女にとって上総時代は孝標と多少しっくり行かなかったことがあったにしても、県知事夫人として召使にかしずかれ、明るくて頭の良い姉妹の家庭教師役も結構楽しかった(そう家庭教師も子供ができる子だと教える方も楽しいのです)。帰京後また宮仕えを始めたら女房仲間とのおしゃべりの中で、どうしてもこの時の話が出てきます。聞くほうも見知らぬ世界の話を聞きたがったでしょう。だから自然に人が彼女のことを上総の太輔と呼んでしまうのです。自分でこう名乗ると決めたという訳でもなく仕方がないのですが、孝標にすれば袖にされたことを、いつまでも思い出させられていい気分ではなかったのです。これが彼の器量だといえばそれまでですが、これも人間ですよね。
平安中期に流行った神楽歌、催馬楽
更級作者が継母に送った歌の元歌は神楽歌『朝倉』です。平安時代にも民衆から殿上人まで歌われた流行歌があり、それが神楽歌、催馬楽です。多くの歌詞は地方で歌われていた民謡(労働歌、戯れ歌など)がもとですが、それに都で管弦の伴奏がつけられ、一条天皇の御代には大いに流行ったそうです。『朝倉』の元歌は筑前国の斉明天皇行宮に因むものと思われます。残念ながらどんな節回しで歌われていたかはわかりません。
本
朝倉や 木(き)の丸殿に 我が居れば
末
我が居れば 名告りをしつつ 行くは誰
<現代訳>
本:朝倉の黒木の御殿に私が居ると
末:私がいると、名乗りしながら行くのは誰だろう
※名告り(なのり):宿直などで自分の官名などを名乗りながら、巡回すること。
元歌では木の丸殿、つまり製材しない丸太で作った宮で「きのまるどの」と読ませますが、更級作者の歌では、「このまろ」と読ませているところにユーモアがあり、継母も思わず、にっこりというところではないでしょうか。はやり歌をうまく使って言いにくいことを伝えるとは、さすがです。
「神楽歌 催馬楽 梁塵秘抄 閑吟集」p.127 日本古典文学全集25、小学館