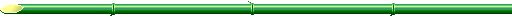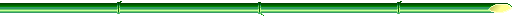伊賀国在庁官人解に見る東大寺荘園における徴税
平安時代後期の徴税、特に荘園における国衙、領家(寺家)、領民の間で課税、税収の配分は当時の経済システムを知る上で重要である。
ここでは、伊賀国東大寺封戸黒田庄等の争いで取り交わされた文書には当時の徴税システムの一端がのぞいている。(平安遺文 1958号、平安遺文古文書編(5)p.1711、東京堂出版)
登場する伊賀国名張郡黒田庄、鞆田庄、玉瀧庄は東大寺の封戸に指定されており、伊賀国は税収の一部を東大寺に収めなければならなかった。律令制の下では国衙は徴収した税の内、封戸に正税の半額、調庸物の全部を封主に納めるのが原則であった。延喜・天暦の改革以後、班田収受制は放棄され、税は土地課税へと変化した。新たな税制は生まれたものの、課税基準を示す法令ははっきりせず、平安中期に至り慣行として田地1段につき米穀3斗という公田官物率法が定着した。しかし全国一律の税率ではなく争いが起こることもあった。
この解文で税滞納を責められている3つの荘園は隣接した場所ではなく、ばらばらに存在する。伊賀国には東大寺庄園は、あと5箇所あるが、そこは段当り3斗を納めている。未納3箇庄は元々東大寺の杣(用材切出し)で耕地が少ないため、出作をしていた。出作地がどこにあったか不明だが、どこであれ、収穫を上げるための投入コストは増える。その辺から、この争いが始まっていると想像できる。天治2年(1125年)伊賀国検田帳(平安遺文2058号)によれば名張郡黒田庄は田25.85町、出作247.96町であり、出作で大半の収穫を得ていたことがわかる。
以上を念頭に該当の東大寺文書を現代語で読んで見よう。原文、書下し文はこちら。
伊賀国在庁官人解の現代語訳
伊賀国在庁官人の解 重ねて申文の事、提出させていただきます。
東大寺庄園、黒田、鞆田(ともた)、玉瀧の三箇所の住人等は出作(でづくり)の公田官物を収めません。また併せて従来の税率に反し、1段当たり米穀3斗の(税の)うち1斗を減らせと屁理屈をこねる事態になった経緯を説明させていただきます。
国内官物率法では
- 別符
- 米穀3斗/段
- 公田
- 米穀3斗/段(1斗を京庫)
- 准米 1斗7升2合/段
- 油 1合
- 稲 1束
- 穎稲 2束
- 院 御庄出作公田段別
- 米穀3斗
- 准米1斗7升2合
- 穎稲3束
添付資料
段別米穀3斗納税済証文 1通 (東大寺庄黒田・鞆田・玉瀧三箇庄例(済例))
未進注文1通
状況を調べますと、問題の東大寺領三箇所の住人等は、公田350町を好き勝手に出作し訳もなく所当官物を納めません。そこで状況を(お上に)申し上げたら早く納めさせるようにと、寺家(東大寺)の指示は数度に及びました。なのにその住人らは、ああだこうだ云って承知しません。去年の収納の期限は過ぎてしまい、今年三月には、もう次の農業の季節が来るのに遂に納めませんでした。もし、この寺家(東大寺)の指示が内外にあったのに、そうしない、庄民等はどういう根拠で納税できないというのでしょうか。そもそも、問題の出作の公的税率は従来から段当り3斗です。しかしながら、これまでの納税の例に背き、段当り現米2斗納税ということを無理やり言い張るので、お上にお伺いを立て、公田の税率通りに納税させるように宣旨を下されたばかりです。それなのに、そこの住人、僧慶暹(けいせん)は前々任の名張郡納所の書生で(現任の源)朝臣兼国の指導をしていた者ですが、其の時は反当り現米3斗を完済しております。どうしてその例を忘れ、今になって屁理屈をこねるのでしょうか。何をかいわんやです。院の御庄五箇処は当国第一の栄えようです。問題の出作公田官物は段当り現米3斗ですが、あえて異論は出ていません。どういう理由で多かったり少なかったりする議論になるのでしょう。こう云えばああ云う、その寺家住人等の所行は終わりません。非難してもキリがありません。早急にこの言いがかりを止めさせ、宣旨通り、院の御庄の例、反当り現米3斗納めさせられるようご裁下くださるよう子細を申し上げ、重ねて言上いたします。
保安3年2月 日 散位源朝臣為宗 (他9名、略)
用語説明
- <出作(でづくり、でさく)>
- 古代から中世にかけて特定の所領の住人が、他の所領の土地を耕すこと。特に荘園の住民が付近の公領を耕作する場合が多かった。
- <別符>
- 公領や荘園の領域内で、本来の領主(国衙、領家、社寺)以外の開発者に与えられた耕作地で賦課物の一部が与えられた。富裕農民層が荒廃田や新開地を開発した見返りとして所有を認められた。
- <院御庄出作公田>
- 院とは白河上皇と考えられる。上皇によって設置された荘園か。院御庄は、いわゆる便補保(びんぽのほう)に当たると思われる。
- <見(現)米>
- 旧来の正税に当たるものか。解文には「見米」と表記されているが、現物の米穀という意味で「現米」と記すべきものと考えられる。
- <准米>
- 旧来、賦課されていた調庸物に見合う米穀という意味で「准米」。調庸物は中央上進であったから京都に納めるべきもの。
- <荘園の現在地>
- 黒田庄:三重県名張市黒田(黒田堂ヶ谷観測所)
鞆田庄:三重県伊賀市中友田305-15(鞆田郵便局)
玉瀧庄:三重県伊賀市玉瀧3506-7(玉瀧郵便局)
解文が示す平安時代中期から後期の課税構造
田地にかかる税は平安時代前期の正税と調庸物の2本立てが形を変え、現米と准米になっている。課税基準は人ではなく田の面積である。納税する財物は、一部の例外(油など)を除き米に統合されている。解文に示される賦課された税が中央、国衙、領家でどのように配分されるかを以下の表に示す。
表 伊賀国における課税田地と分配先別の税率(段当り)
| 国衙 | 中央 | 封主(東大寺) | |
|---|---|---|---|
| 別符 | 現米5斗 | ||
| 公田 | 現米3斗(内1斗京庫) | 准米1.72斗、油1合、現稲1束、穎稲2束 | |
| 院御庄出作公田 | 准米1.72斗、穎稲3束 | 現米3斗(黒田庄民主張2斗) |
上の表から次の事が推論できる。
- 私領の発生
- 班田収受制とは無関係に設置された別符では現米、純米の区別なく現米5斗と一発収税である。中央には税は渡さないという意味で私領である。
- 地税の米穀収税への一本化
- 公田では現米、准米二本立ての収税で、形骸化しながらも調庸物収税が残っている。実質的には油など一部例外を除けば米穀一発収税である。
- 輸送・倉庫・金融業者の発生
- 准米は旧来の調庸物購入に充てられると見られる。しかし中央官庁が其の米穀を使って必要物を購入する筈はなく、国衙の役人が輸送・倉庫・金融業を営む業者を使って物品を調達し納入するのであろう。公田の現米の内1斗は京庫に納入されることになっている。おそらく大津あたりに置かれた伊賀国納所の運営経費に充てられるのではなかろうか。