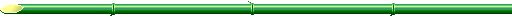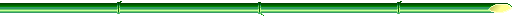今昔物語集(巻第29)に見る平安時代の人身売買
平安時代の治安は畿内を除けばなきに等しい状態だった。殺人・放火など重罪を除けば諸国の国衙はほとんど動かなかったのではないだろうか。畿内で起こった事件については貴族の日記に表れるが、地方では知られることもなく闇に葬られていたと想像される。
今昔物語には多くの犯罪が語られている。多くは実際の事件をもとに脚色、誇張して面白い話に仕立てているが、事実ではなくても、社会の一面を知る手掛かりにはなる。ここでは誘拐事件を取り上げる。人口の少ない農村が大部分の時代にあっては、人手を要する仕事があっても、なかなか人を集める手段はない。例えば繊維品の生産には多くの手作業を要するが、農村にそれほどの余力はない。そこで登場するのが、人買い、誘拐団である。彼らはいろんな手段で、子供から大人まで、特に抵抗しない女性は恰好の餌食で、家族の探索が及ばない遠国に連れて行き売り飛ばす。そういう人を買うのは、繊維品工場を経営している元郡司であったり荘園を管理する荘官たちであろう。労働集約的仕事は手先が器用で根気強い女性に向いている。ここで取り上げた近江の女性は美濃国に連れてゆかれ、恐らく絹、布の生産に従事させられるところだったのだろう。主の従者であった男は亡くなった主人の若奥さんを、代価として絹や布で売り飛ばした。買主は彼女に仕事を仕込み、朝から晩まで奴婢として使う予定だったのだろう。結局、女性は食事を受け付けず死んでしまったが、そのことをこの買主は京都に行った際しゃべっている。現代なら誘拐罪で警察が飛んでくるところだが、平安時代には何のお咎めもなかった。
以下引用
(原文はカタカナで書かれているがひらがなに改めた。被害者の年齢を鈴鹿本(小学館版)では四十ばかりとしているが丹鶴本(新潮版)では三十ばかりとなっている。話の筋からはこちらの方が理にかなっている。繊維労働者なら若くないと使いものにならない。卅と卌の書写ミスであろう。)
近江国の主の女を美濃国に将(い)て売る男のこと(第24)
今は昔、近江の国〇〇郡に住むものありけり。未だ年も老いぬほどに失にければ、其の妻も未だ年三十程にてぞ有りける。子一人も産まざりけり。京の人にてぞ有りける。
其の夫の失たるを強(あなが)ちに恋悲みけれども、甲斐無くて、京に上りなむと思ひけれども、京にも打ち憑(たのむ)べき人も思えざりければ、思ひ繚(あつかひ)て有ける程に、年来付仕ひける男の、万に付けて後安く翔(ふるまひ)ければ、夫失せて後は、此れを打ち憑みて何事も云合せて過ぎけるに、此の男の云はく、「此(かく)て徒然(つれづれ)にて、御(おはせむ)よりは、此より近き山寺の候ふに御まして、暫く御湯なども浴させ給ひ、御行(ありき)なども心静どかに為させ給へかし」と勧めければ、女、「実に然も有る事也」と思て、「然様(さよう)に近き所ならば、行なむ」と云ければ、男、「近き所に候ふ。何でか愚かならむ事は申し候はむ」と答ふれば、女、「京にも上りなむと思へども、京にも祖共も無く類親も無ければ、然様ならむ所に行きて尼にも成らばやと思ふぞ」と云ければ、男「然て御まさむ間の事は、己こそは繚(あつかひ)奉らめ」と云へば、女只出立に出立つ。
女をば馬に乗せて、男は後に立ち行けるに、近き所とは云つれども、遥に遠く将行ければ、女、「此は何かに此くは遠きぞ」と云ければ、「只御(おはし)ませ。よも愚なる事は仕らじ」と云て、三日許将(いて)行にけり。然て人の家の有る門に、女をば馬より下して、男は家の内に入ぬ。女、「此は何かに為る事やらむ」と心も得ずねども、待立てる程に、男返り出て女を内へ将入ぬ。板敷の有るに畳敷きたる所に居へたれば、更に心も不得で女見居たれば、此の男に家より絹や布などを取らす。「此は何事にて取するにか有らむ」と思ふ程に、男此の物を取るまヽに、逃る様にして去ぬ。
其の後に聞けば、早う、此の男謀(はかり)ける様は、此の主の女を美濃の国に将行て売つる也けり。然て目の前に直を取て行く也けり。女此く聞て、「奇異(すさまじ)」と思て、「此は何かに。我れをば然々云てこそ山寺へとて将(いて)来しか。何(いづく)かに此は」と泣々く云へども、耳にも聞き入れずして、男は直を取て馬に這乗て馳て去ぬ。
然れば女泣居たる程に、其の家の主、「女を買得たり」と思て、女に事の有様を問ければ、女、「然々也」と本よりの有様を語て、涙を流して泣けれども、家の主も耳にも聞入れずで有けるに、女只独りにて、云合すべき人も無く逃べき様も無かりければ、泣悲むで云ける様、「我れを買取り給て、更に其の益有らじ。極(いみじ)く、我れを殺し給ふとも、我が世に有可(べ)くはこそ」と云て、低臥(うつぶしふせ)にけり。
其の後、物など持来て食せれども、露起上る事も無かりけり。云はむや努々物食ふ事は無かりければ、家主も思ひ繚(あつかひ)て有」、亦従者共は、「然りとも、暫こそ嘆き臥たらめ、遂には起上て物も食てむ。只、御覧ぜよ」など口々に云けれども、日来を経て更に起上らざりければ、「稀有也ける奴に て」など思ひ死に死けり。然れば家主云ふ甲斐無くて止にけり。
此れを思ふに、尚極く事吉く云ふとも、下衆の云はむ事には付くまじき也。
此の事は其の家主の京に上て語けるを聞伝へて、「糸奇異(あさまし)く哀れ也ける事かな」と思て、此く語り伝へたるとや。
出典:今昔物語集巻29第24話p.399、日本古典文学全集(四)、小学館