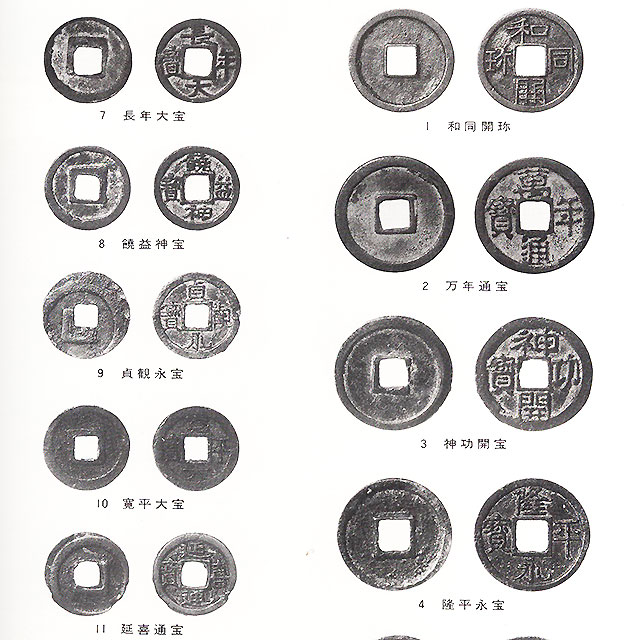浅草から日比谷入江
日比谷の入江、寛仁4年19日グレゴリオ暦10月14日曇り
日がかなり高くなった頃、隅田川を渡り武蔵の国に入る。隅田川は大河で、あちこちに島や州があり船はその間を縫うように下り船着場に着いた。ここは昨日渡った太井川のようにすぐ対岸でなく、かなり下ったこんもり繁る森のある場所にある。今日は川を渡るというよりちょっとした船旅気分。でも川を遡って船が戻るのに時間がかかり、荷物の方は昨日の午後からずっと渡していたが間に合わず、今日も朝から荷渡し作業が続いたのだ。隅田の渡しは距離も長く、州が多く危険なので太井川のように夜には船を出さない。そのおかげで今朝は、ゆっくり食事を楽しむことができた。朝から、川魚のあぶったもの、サトイモの煮物に柔らかいご飯、結構豪勢でしょう。出入りの商人が
「この隅田は上流の在所の米や野菜、近くの川や海の魚介類が集まってくるので、おいしいものでも何でも揃います。」
宿の仮屋の立つ場所から川岸を見下ろすと朝の食事を用意する煙と川から立ち上る霧が一緒になってたなびき、絵のような景色が広がる。多くの人馬が動き回り、これまでのさびしい宿とは様変わりで人のやっていることを見ているだけでも心が浮きうきしてくる。すぐそばでは鳶丸が先ほどまで煮炊きに使っていた柄付きの大鍋を片付けている。二人で持ち運びする大きなものだが、今度の旅では3個も持ってきたのに全員の食事をまかなうのは大変で炊事係は毎日てんてこ舞している。
荷物を渡し終える頃、ユリがやってきて、ちゅう木を手に、
「姫様達、準備はいいですか、出発ですよ。置いてゆくものは置いてきましたか?なんならお供しますよ。」
今なら男達も忙しく周りに人もいないので茂みに用足しに入っても安心してできる。姉さんと顔を見合わせ
「二人で行って来るから先に川岸に行ってて」
と姉が答えた。 向こう岸には既に荷を積み終えた馬や車が勢ぞろいしていた。周りを弓や薙刀を持った侍たちが警備し、虎吉はじめ菅原家の家人たちが荷物の積み残しがないか点検している。馬借や車借はもちろん、こちら側で商売している者達で顔ぶれは全員変わった。ずっと変わらないのは侍たちで、もう何日も一緒に居るので、すっかり顔と名前を覚えてしまった。馬に跨った千葉三郎が私たち家族が船から下りるのを見つけるとカッカッカッと近づいてきて
「皆さん、お待たせしました。待ちくたびれたでしょう。あーその辺ぬかるんでいますので足元に気をつけてください。」
三郎は父より継母や姉を気遣うように声をかけながら馬を下りた。実は三郎は私や姉とはずっと前から顔なじみだ。というのは彼は私の遊び仲間の桔梗ちゃんの兄なのだ。年齢は姉より一つ上の十七歳だが、もう武者ぶりは一人前の大人と変わらない。
彼の父、経基は上総国府の在庁官人で掾(じょう)を勤めている(上総では菅原孝標の官職であった介(すけ)が実質上の国守、掾はその下の次官、今なら副知事)。言ってみれば上総では一番の実力者で役所を取り仕切っている。父の話では上総の千葉氏はこの地方では古くからの豪族で先祖は平氏の流れとか。でも千葉氏一族の内部でいろいろ争いごとが絶えず、しょっちゅう刃傷沙汰があって、三郎の父は役所の仕事のほか、その仲裁やら処理に手を焼いているそうだ。私は三郎しか会ったことはないが、彼には二人の兄が居て父を助けている。三郎は本当は良基という名前だが三男なので皆から三郎と呼ばれている。桔梗ちゃんも本当は寧子(やすこ)というが普段その名を呼ぶことはない。上総に来て一と月くらい経った頃かしら、彼女は父経基に連れられて初めて私の家に来た。
「田舎育ちで何も知らないので、都の礼儀作法を教えてやって下さい。」
と、まま母さんに頼んでいった。その実、父が、私の遊び相手にと経基に頼んだのは見え見えだった。でも、そんなこと私たちにはどうでもいいんだ。二人はとても仲良しになれた。彼女は言葉こそ東言葉で話すときも恥ずかしそうにするが、桔梗ちゃんはいろんなことを知っている。庭で遊んでいても草や花、虫のこと、何でもよく知っている。花輪の作り方、虫の音の聞き分け方などいろんなことを教えてくれた。彼女を普段、送り迎えするのが兄の三郎で、直接話をすることはあまりないが彼とは古い顔なじみなのだ。
昨年、浜のお社(現在の飯香岡八幡宮)の祭礼に私の家族全員もお参りしたが、その時、経基の家族も一緒で、三郎はその時具足をつけて警護の役を務めていた。彼の武者姿は始めて見たがそれは立派で凛々しかった。特に馬上姿は素晴らしい。それというのも彼は馬を扱うのが上手で、自分の思うように馬を動かせるのだ。馬というのは荷物や人を運ばせるのに便利だが、それは言うことを聞いてくれるうちで、機嫌が悪くなると手に負えない。馬借の馬方は一日中、馬に毒づいている。
半年ほど前、家に来たとき、まま母さんに
「今度、都までご一緒させていただくことになりました。都のことは何も知りませんのでいろいろ教えてください。」
と無口な彼が、うれしそうに挨拶して行った。父の話では二人の兄は上総で持ち上がっているごたごたから目が外せず、まだ若い彼にお鉢が回ってきたらしい。
「三郎兄ちゃんは今度都に着いたら新しい具足をあつらえてもらうんだって。今は家にある古いのを使っているけど、兜もないし、あちこち破れているしね。兄ちゃん今度の旅をとても楽しみにしているのよ。私も行ってみたいな。都ってどんなとこかしら。でも私なんか一生都に行くことないよねー。姫様も都に帰ったら私のことなんか忘れてしまうだろうし。」
と遠くを見るような目でため息をついた。
「そんなことないよ。都に戻ったら手紙書くから必ず返事を書いてよ。」
と答えたものの、都に帰るのを一番楽しみにしているのは、この私自身で言葉もうわの空だったろう。 全員が揃い行列が動き始めた頃、空模様が怪しくなってきた。
「少し急いだ方がよさそうですね。何とか降り出す前に竹芝の寺に着けるといいんですがね。足元が悪いんですが、近道の日比谷入り江の濱道を通るので何とかなるでしょう。」
どうやら日比谷の浜道を通るらしい。道がしっかり固まっていないので通りにくいが、上り下りがなく、近道なので荷物がないときに使う道である。こんなに荷物があるときは台地の上の道を使うと聞いたが。
川岸に沿って南に進むとちょっとしたお堂が見えてきた。この辺では有名な由緒ある観音堂(現在の浅草寺)だ。ここで暫く馬を休ませる間、車から降りてお参りする。狭い車から降りて足を伸ばし、周りを一回りすると、いい気分だ。鳶丸が水桶を持ってきて椀で水を飲ませてくれた。小高くなった境内に上るとお堂の周りには何軒も、もの売りの店や家、屋敷があり、国府のある村のように賑わってっている。
「ここのご本尊は川から流れておいでになったのですよ。」
どこからともなく、干魚を盛ったざるを頭にのせた女が近づいてきて頼みもしないのに説明を始めた。
「ずっと昔の話で、女の帝(推古天皇)がいらっしゃった時代だそうです。檜前(ひのくま)の浜成、竹成という漁師の兄弟がこの辺りで暮らしておりました。とんでもない大雨の降った後、食べるものもなくなり雨も止んできたので恐る恐る舟を出したのです。舟といっても木の葉のような舟ですよ。うねる波にもまれるようにして網を下ろし舟にしがみついていると、何か重たいものが網にかかったように舟が引きずられるので、あわてて岸に戻り網を引き上げると、なんと金色に輝く仏様が網の中に居られたのです。仰天して村長に届けると主だったものが相談して『これはきっと、この里に福をもたらすためにお下りなされたのだ。手厚くお祭りしよう。』ということになり、最初は粗末なお堂だったそうですが、今ではあちこちから寄進も受けて少しは立派なお堂になっています。いや都のお寺から見れば堂ともいえないものでしょうけれどね。ここの仏様は観音様でそれは慈悲深く霊験あらたかなんですよ。私は毎日この川で取れる魚を売って命をつないで来ましたが、商いに出る前に必ずこのお堂の前でお参りをするんです。私と二人の子供を生かすため、この殺生をお許しくださいとね。お蔭様で亭主は二年前に漁の最中、川に落ちて亡くなったのですが、何とか生き延びてきました。」
長い話の後、女は深々とお堂に向かい合掌した。気がつくと小さなぼろを着た子が二人、女の着物の裾を引っ張っている。まま母さんもすっかり同情したのか、感心したのか、鳶丸を呼び
「あのお魚おいしそうだから買ってゆきましょう。」
女はとたんにニコニコ顔になり頭を下げつつ、ざるを持って鳶丸の後についていった。それを目で見送りながら、三郎は
「あの女はいつもああやって商売しているそうですよ。この辺では有名な商売上手です。」 まま母さんは、向こうで代金の米をざるにあけてもらっている女を見やりながら
「でも、いいじゃないの。それで生計が立てられるんだもの」
行列が動き出し暫くは川沿いの道を下流に進む。季節は完全に秋になり川原の葦も枯れ始め、朝夕は風が冷たい。私たちは着物を一枚余計に着込んだが荷を運ぶ人足達は相変わらず粗末な単(ひとえ)一枚きりだ。慣れっこになっているのか、あのまま本格的な寒さが来るまで着たきり雀なのだ。
「衣類はとても高価だから、できるだけ辛抱して着ないようにして長もちさせるのよ。食べるだけでも大変なんだから。」
と姉が言う。
「この前、上総であの人足たちが着ているようなボロを着た女たちが襲われて身ぐるみ剥がされたんだって。畑の帰りで何人も一緒だったから油断していたのね。いくら何だって貧しいものから取り上げなくてもいいのにね。私たちはこうして侍たちに守られているから襲われないけど、ちょっとでも隙を見せるとカラスの大群のように盗賊がたかってくるのよ。」
と、まま母さんが続け、声を潜め
「最近は田畑も荒れて稼ぎが悪いので、どうしても手っ取り早く人から奪いたくなるのよね。皮肉なことに今一番の商売は侍になることだって。確かにいくら長者だ、金持ちだって言っても、それを守らなくては意味がないからね。百姓でも腕に自信がある男達は、土地の有力者の郎党に雇われる方が、はるかに実入りがいいのよ。もちろん何かあれば命懸けだけどね。今度の旅で警護の責任者は千葉三郎だけど実際はいつも虎吉と馬を並べている源造が侍たちを仕切っているの。何か事があるといつも先頭で戦う勇者だそうよ。三郎はまだ若いから、父親の経基が付けてくれたの。上総では有名な武芸者で弓矢、薙刀はもちろん、組討ちでもかなうものがないそうよ。これまでいくつか合戦に出て、敵の首をいくつも取っているんだって。おー怖わ」
「そういえば恐ろしい顔してるよね。話をするのは聞いた事がないけど、睨みつけられたら、どんな相手でも逃げ出しそう。」
源造は歳は三十くらいだろうか。獰猛な顔をしているが三郎には何かと声を掛け、三郎も彼を頼りにしているようだ。案外普段はやさしい性格なのかもしれない。
道の右手にはこんもり盛り上がった森が連なり、それが尽きると小さな流れに出た。車から降りて、丸太で作った橋を渡る。この辺りに詳しい人足が
「冬になる頃には隅田川からたくさんの水鳥があの丘を越えてあちら側にある沼(現在の忍ばずの池、今は埋められてない千束池、小石川沼)に渡ってゆくんですよ。大変な数の白い鳥が空を覆うように渡る様は本当に神様がお渡りになっているような感じがするんです。あの丘の頂上には木が茂ってここからは見えませんが白鳥明神(現在の鳥越神社)というお社があります。」
と教えてくれた。
雲がどんより低く垂れ込める空の下、前を行く馬に乗った三郎の持つ弓が隠れるほど高く伸びた蘆原をかき分けかき分け半時近くも進んだ頃、突然目の前に海が広がった。正確に言うと日比谷の入り江だ。大きな湖にも見えるが濱に打ち寄せる波で海だということが分かる。左手が東で松原が茂りその向こうが外海(東京湾)になっている。これから右手に回り込み濱づたいに南に下ってゆくことになるが、その前に、ここで小休止し、皆に今朝ゆでた里芋が配られた。私たちは皮をむきながら食べるのだが、人足たちは皮ごとうまそうに食べている。腹が減っているのか、あっという間に食べ終わり、物足りなげな顔をしているが、今日の宿泊地竹芝寺に着かなければ食事にはありつけない。
この日比谷の海はとても薄汚い。曇っているせいもあるが、これまで通って来た、上総下総の白砂青松の美しい海岸とは比べるべくもない。浜も砂ではなく黒い泥で汚く、浜辺には葦が立ち枯れて生い茂り、腐ったいやな匂いもする。ただ葦の間には水鳥が多く、いろんな鳥がこの入り江を飛び回っているのが救いかな。狭い道が小高い丘が入り江に落ち込む裾を縫うように伸びている。やっと二人が並んで歩けるくらいの道で、地面は水溜りばかり。ここから車を降ろされ歩いてゆくことになった。こんな道を一里も進みやっと入り江の向こう側に出ることができた。この間、荷物を積んだ車はあっちこっちで泥にはまったらしく、大分遅れて入り江の浜道から出てきた。こんな悪い道では車より馬のほうがいい。馬はちゃんとぬかるみを避けて歩くから。
父と一緒に、汗をぬぐって一休みしているところに虎吉がやってきて
「殿、ここまで来ればあと一息です。この台地の上に上がってしまえば多少上り下りはありますが、道もしっかりしていますし降り出す前に竹芝の寺に着けそうです。泥に落ち込んで車が一台壊れましたが、明日は寺に逗留するので修理できるでしょう。寺のほうには今朝、先に人をやっていますので、もうお迎えの準備はできていると思います。」
「そうか。ご苦労だな。じゃあ、あと一息頑張るか。まあこの辺はまだ盗賊の心配がないだけ気が楽だな。」
父は馬には乗るものの、自分では馬を思うように操れず、いつも轡持ちがついて居る。そんな都育ちの主人たちを見下ろすように、坂東武者達が軽やかに周囲を駆け回るのを目で追いつつ、まま母さんが姉さんに向かい
「三郎は絵に描いたような武者ぶりだねー。あれに都で立派な鎧兜をあつらえたら、惚れ惚れして上総に返せなくなるかもね。」と言った。そして、いたずらっぽく姉さんの顔を見やると、姉さんは黙ってあちらを向いてしまった。
雨粒が落ち始め、空が泣き出すように暗くなった頃、竹芝の寺に着く。
浅草寺駒形堂

浅草寺駒形堂。東京都隅田川に架かる駒形橋のたもとにあり、これが浅草寺創建時の名残といわれる。堂の背後に隅田川が流れる。今は立派なお堂だが、その昔、上流から流れてきた観音様を祭ったのは草ぶきの質素な草堂であったとか。浅草寺が立派な伽藍を持つようになるのは鎌倉時代からである。
メイン画像は『浅草寺縁起』(浅草寺蔵)応永年間の作とされる。
鳥越神社

鳥越神社。651年の創建と伝えられ往時は小高い丘の上に鎮座し白鳥神社といわれていた。この社は徳川家康江戸入府以来行われた江戸市街開発の際、山を切り崩し平地化された際、移転を余儀なくされたが、氏子らの強い願いで造成が完了したのち、同じ地に再建された。その意味でランドマーク的価値がある。