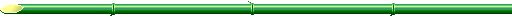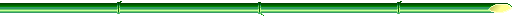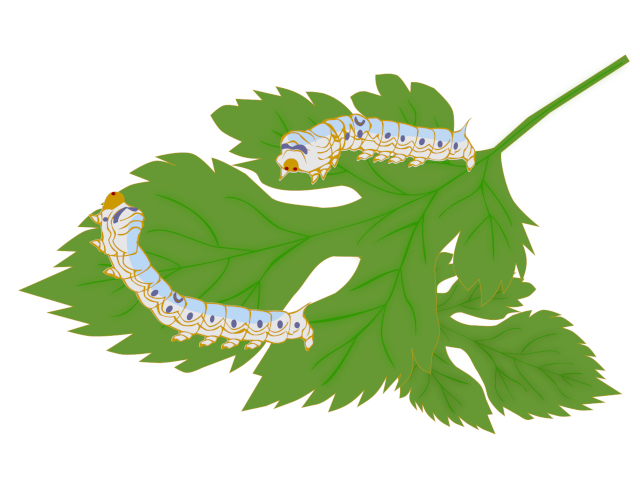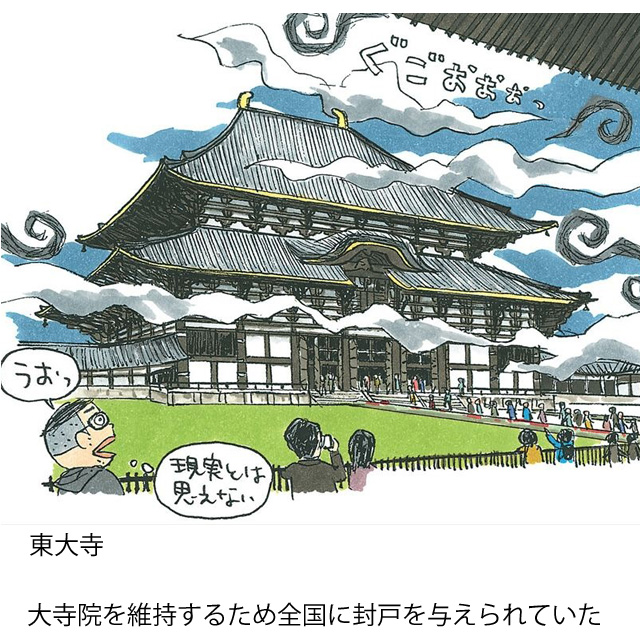平安時代における富・財貨の移送方法(大津湊の役割)
更級日記の旅、最終場面には近江の湖東を淡々と過ぎ、遂に“粟津”に着くまでが描かれている。さて京を目前にして何のために粟津に逗留したのだろうか。京都の外港、大津と粟津はどのような場所であったのだろう。琵琶湖は巨大な水路であり湖北の塩津を通じて北陸道、湖西は勝野を通じて若狭、湖東は朝妻から東山道、東海道へと通じ、瀬田川を下れば奈良方面にも通じていた。更級日記は次のように語る。
『そこ(小野荘か)を立ちて、犬上、神崎、野洲、くるもとなどいふ所々、なにとなく過ぎぬ。湖のおもてはるばるとして、なでしま、竹生島などいふ所の見えたる、いとおもしろし。勢多の橋みなくづれて、わたりわづらふ。
粟津にとゞまりて、師走の二日京に入る。暗くいき着くべくと、申の時ばかりに立ちて行けば、關ちかくなりて、山づらにかりそめなるきりかけといふ物したる上より、丈六の佛のいまだ荒作りにおはするが、顔ばかり見やられたり。あはれに、人離れていづこともなくておはする佛かなと、うち見やりて過ぎぬ。こゝらの國々を過ぎぬるに、駿河の清見が關と、相坂の關とばかりはなかりけり。いと暗くなりて、三條の宮の西なる所に着きぬ』
ここ粟津は前国司として菅原孝標が最後の仕事をやり遂げる場所であった。彼は4年間の勤務で少なからぬ報酬を得たものの、実際にはまだ何も形ある富にはなっていなかった。琵琶湖に面する港、大津と粟津は北陸道や東国からもたらされる物資、人の集散地であった。
京都は巨大な消費都市で莫大な物資を消費する。その物資の過半は琵琶湖の港、大津や粟津に陸揚げされ、そこから陸送で逢坂峠を通り、洛中に入る。大津の南に連なる粟津はほぼ一つの港と考えられる。平安時代にこの港湾には、後世の物流倉庫やそれを支える運輸業者その他、インフラのさきがけに当たるものがあった。同時代の蜻蛉日記は大津湊の様子を次のように描いている。
『行先遠かるに、大津のいとものむつかしき屋どもの中に引き入りにけり。それも珍らかなる心地して行き過ぐれば、遥々と浜に出でぬ。
来し方を見やれば湖面(うみづら)に並びて集まりたる屋どもの前に、船どもを岸に並べ寄せつゝあるぞ、いとをかしき、漕ぎ行き違う船どももあり』
『かげろふ日記』(棶あふちの木陰)、p.192、日本古典文学大系20、岩波書店
この的確な描写は浜に向かう道の両側にごちゃごちゃと店が立ち並ぶ港町の喧騒を伝えている。浜に出て、振り返って見れば、浜に沿ってずらっと倉庫が建ち並びその前に船が着けられていた。規模こそ違え、現代にも通じる波止場の風景である。

(法然上人絵伝播磨国高砂浦)
このページでは平安時代中期において富や物資流通の要であった琵琶湖岸の湊、大津・粟津でどのような経済活動があったかを見る。物々交換経済の社会で遠隔地から戻った菅原孝標がいかにして富を現実の価値に替えたかを知る手がかりはここにある。章末に菅原家の粟津での経済活動を仮想的に再現してみた。
(1)平安時代における諸国納所の存在と機能
菅原孝標が上総で蓄えた報酬は現代人の感覚で言えば半端ないものであった。この多くは米穀で支給されている。更に私的な利殖によって得た財物も蓄えられていた(利殖とは言っても現代感覚で言えば非常にグレーなものもあった)。その富の大半はこの時点で、絵に描いた餅でしかなかった。問題はこれを京都で具体的な財物に替えて、その後の生活に生かすことである。全国を網羅する金融機関がない時代にあって、どのような具体的手段で財貨を京都に移送し活用したのだろうか。
①港に置かれた納所(なっしょ)の存在
諸国の国衙や大寺院は大津、淀、木津など重要な船着き場に「納所」を置いていた。一般に「納所」とは11世紀以降見られた国内の郡、郷に置かれた税の収納所であるが、それとは別に中央への貢納物上進のために京都周辺に置かれた出先機関が大津納所、淀納所であった。京都伏見区淀には現在も納所(のうそ)という地名が残る。西岡虎之助氏は古代において諸国からの都への貢納品の搬出、搬入のために設けられた荘園の倉庫が中心となり港湾集落となってゆく過程を諸国の事例をもとに論証している(「荘園における倉庫の経営と港湾の発達との関係」(『荘園史の研究(上)』p.111~、岩波書店)。
下に示す文書は越後国にあった東大寺封戸の鮭の取得分を越後国の出納係秦成安が越後国「大津納所」の責任者助方に払出すよう命じた切符控えである。
------------------------------------------------------------------------------------------
越後国雑掌秦成安解 東大寺御封代鮭を進上申す事(平安遺文663号)
合せて3278.5隻
右去年の料、進上件のごとし、以て解す。
永承3年7月5日 雑掌秦成安
東大寺切符案(平安遺文664号)
下す 大津納所 助方
鮭3301隻下し奉るべき事 正物3278.5隻、車力32隻
右越後国永承元年、去年の二年料下し奉ること件のごとし。取請うべき文
永承3年7月5日
----------------------------------------------------------------------------------------
上記の切符で”大津納所”の実在が確認される。又東大寺納入の鮭3278.5隻請求に対し、切符では車力代32隻を加えて払い出されることに注目したい。但し、車力代は大津納所が受け取る。
②大津納所の機能
物資の集散地である大津納所で行われていた業務について、西岡虎之助氏はその一端を伝える東大寺若狭国封米の決算報告にある大津召米注1の内容を紹介している(荘園史の研究(上)p.143、岩波書店)。
東大寺御封米のうち「大津召米」と書かれている項目の内容は 東大寺、大津納所での出納内訳を記載したものとみられる。
注1:平安遺文900号、平安遺文・文書編(3)、p.951、東京堂出版。(若狭国東大寺御封米結解、平安遺文900号原文参照のこと)
注.2 原文の大津召米73.18石の下に『正米66.53石、車力6.65石』と割注がある。ところが車力代に見合う納所得文米を西岡氏の著作論文p.144では7.10石としているが、これは良珍請神祭料0.5石を0.05石と間違えた計算ミスによるもので6.65石が正しい。
表.1 東大寺若狭国御封のうち大津召米内訳
| 項目 | 内訳 | 数量(石) | |
|---|---|---|---|
| 大津召米 73.18石 |
送寺家米 36.42石 |
東大寺 上 松男請、天喜6年3月13日納 | 30 |
| 運駄30疋賃、疋別2斗 | 6 | ||
| 舟賃間食料30人、1升4合 | 0.42 | ||
| 納所支配米 30.11石 |
雑仕女度々請往来 | 4.87 | |
| 工国為度々請往来 | 8.16 | ||
| 威儀師御使長時度々請往来 | 4.5 | ||
| 心経会御仏供料、4月2日下往来 | 0.25 | ||
| 忠安使力丸請、同日下往来 | 6 | ||
| 円秀請工酒料、同日下往来 | 1 | ||
| 岡本君御使勢法請、同日下 | 0.3 | ||
| 工長及請、同七日下往来 | 0.3 | ||
| 長時請工食料、同日下往来 | 0.3 | ||
| 千時請、十一日下往来 | 1.2 | ||
| 威儀師御使長時請、同日下 | 0.1 | ||
| 長時請、四月十三日下 | 0.5 | ||
| 大仁王会御仏供料、廿四日下 | 0.18 | ||
| 良珍請神祭料、同廿九日下 | 0.5 | ||
| 西阿闍梨御母上御忌日料御仏供料五日下 | 0.05 | ||
| 忠安使力丸請御酒料、四月廿九日下 | 1 | ||
| 工国為請、四月廿九日下 | 1 | ||
| 仁王会御仏書使仏食料、雑仕女請 | 0.3 | ||
| (納所支配米小計) | (30.11) | ||
| 車力代(納所得分米) | 大津召米ー(送寺家米+納所支配米) |
6.65注.2 |
<表.1 から読み取れること>
- (a)東大寺封戸米は納所に納入された時点で車力代が天引きされる
- 大津召米73.18石は納所に届いた段階で車力代の名目で6.65石を天引きされる。車力代とは納所管理者(”預り”という)の報酬である。
- (b)納所支配米は納所の維持管理費
- 車力代を除いた封戸米から更に納所の維持管理費(納所支配米)を除いた残りが実際に奈良の東大寺に送られるが、その運賃は別途差し引かれる。最終的に正味30石が寺に届けられる米となる。この慣行を知らない東大寺の出納係は運賃の二重取りではないかとして、争いになることがあった。
その具体例は次の美作国雑掌解に見られる。車力代は名目上、経費を装っているが、実質は納所支配人への報酬として定着していたから東大寺側が異を唱えても無駄であった。下の解は抗議とも恫喝ともとれる内容である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<美作国前雑掌秦成安解(平安遺文661号)>(現代語訳)(原文、書下し文はこちら)
道理と使者請文通り、早く御封勘出状の裁許を願います
右、成安、謹んでいきさつを申上げますと、本件御封は当初から、付随する色々の経費を先に差し引いて、寺家の勘文や牒状に随い初めて処理されました。ところが、今般、(美作)国の勘文を提出しましたところ、承認される筈の、車力代の否認が多くありました。そもそも、使者が正物を請取る場合、車力が真っ先に必要になります。何で今になって車力が否認なのでしょう。すみやかに道理に従い御認め頂くのであれば、これからも誠実にお勤め出来ない訳ではありません。特に若し文書を精査し書類を突き合せてみれば、誤った処理は二十余石になります。どうしてお支払いになっていないのにこのようなことになるのでしょう。 以上
永承3年(1048年)6月2日 雑掌秦成安
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(2)平安時代に発生した民間倉庫業は大津納所が起源か
平安時代にはすでに、民間で倉庫を構え流通業を営む者がいた。例えば「平安時代における遠隔地決済(東大寺上総国封戸からの送金事例)」で前近江守藤原某切符案(平安遺文632号)に登場する“常孝”がそれに当たる。運送についてもこの種の業者が馬借、車借を手配して大津から京都や奈良方面への輸送を行っていたと考えられる。
①民間倉庫業者はどこから生まれたか
大津に設けられた諸国、寺家納所の“預り”と呼ばれた支配人は役人というより、財物、物資の流通管理を担う敏腕手配師であった。前述のように、彼らはそれなりの報酬を得ていて蓄財する機会も大きかった。その蓄積した財貨は現物であるため、別の倉庫に保管する必要が出てきた。このような“預り”は大津には多数いて、その中の或る者は、共同で倉庫を持つものが出てきただろう。彼らは納所を辞めなくても近所に設けられた私的倉庫の管理に関わることができた。
②共同私営倉庫の利点
預り一人の蓄財は小さくても複数人が共同で倉庫を設ければ、各種財物の種類、在庫量も半端ではなくなる。諸国納所の方でも緊急の調達のため煩雑な書面、認証がいらない私営倉庫は便利な存在だったに違いない。また、私営倉庫間での融通も加えれば、大津が一大流通センターになっていたと想像される。ここに運送業との連携があれば流通業の成立となるが、事は簡単ではなかった。
③運送業、苦難の出発
平安時代初期まで運送の専門業者はおらず、農民や荘民が農耕用の馬牛を使って行う臨時の役務であった。ところが納所や民営倉庫業者が発生する10世紀頃になると運送を専門に行う業者が現れた。しかしその馬借・車借たちは権門・勢家の家人たちから妨害され円滑な発展をすることができなかった。権勢家の家人たちは、威を借りて一般の人馬を徴発し彼らの荷を運送させ、人々を苦しめ運送業者の生活をも圧迫し社会問題化していた。これに対し、官はたびたび禁令を出したが功を奏しなかった。
この問題について西岡氏の論文は以下のように述べている。
『大津の貨物を陸路で奈良および京都方面に輸送するには駄すなわち馬力ならびに車力によった。歌人為家が「関越えて暮るれば帰る大津馬おのが一連れ道急ぐなり」と詠んだのは、輸送をおえて大津に帰る駄の様をしめしたものである。当時 大津には、山城国山崎などとともに交通・運輸上の要地であるところから、馬力をはじめ車力に従事する専門業者もすでに発達していたので、貞観九年(867年)には、近ごろ山崎・大津両津頭辺で諸司および諸家人が妄りに威勢を仮りて、しいて車馬を雇うために行旅の人が多く往還にわづらい、傭賃の輩が己に活計を失うなど人民のあいだの愁苦は少なくないとして、強雇を禁止しているが傭賃の輩とは借車(クルマカシ)および借馬(ウマカシ)と呼ばれる労働者すなわち車馬を用いて貨物の運搬に従事し、その運賃によって生活するのを職業とする者で、このような傭賃専業者、権門・勢家の使人たちが一般車馬をしいて徴発しこれに貨物を輸送させるために押されて生活難に陥ったのである。』(西岡:荘園史の研究(上)、p.144、岩波書店)
強雇とは一部の権門、諸院、諸司の配下が百姓の馬や人を強制的に借り上げ荷を京都に運ばせることである。これについては『尾張国郡司百姓等解』31ヶ条の第23条でも訴えられている。この種の訴えに対し、太政官は承和3年(835年)、嘉承2年(849年)、貞観9年(868年)、寛平6年(894年)と繰り返し禁制を加えているが、あまり効果はなかったようだ。大津と京都間には既に馬借車借業者が存在していたが、まだ拡大する経済に対応するものではなかった。また院宮王臣諸司など支配者に権勢濫用の自制を求められる時代ではなかった。
以下に“強雇”を禁じる太政官符の一例を現代語訳で示す。最後の禁令は強盗として処罰することを述べているが効果があっただろうか。
---------------------------------------------------------------
太政官符
諸院、諸宮、諸司、諸家の使用人が行き交う船、車、人、馬を強制的に雇いあげる事(強雇)を禁じる
上総、越後等の国から、また郡、調を運ぶ責任者、郡司、雑掌、運搬人などからも次のような訴えが来ている。
『調物を京へ貢納するには馬を使い、官米を運ぶには船を使うというのが古くからの決まりです。ところが、その輸送の際に前述の使用人らが街道に集まり荷駄の通行を妨害し、船着き場では仲間を集め舟をひっくり返して奪います。ここに至っては馬を奪うのが目的で積んでいる荷物には目もくれません。官納物を紛失し、運送責任者は納品遅滞の責任を取らされます。そればかりか、国内の百姓は運搬責任者を命ぜられ、ひどい目に遭うことを恐れ、他国に逃げ出してしまい国が疲弊する最大原因となります。沿道の諸国に命じて民の苦しみをお救い下さい』
(これに対し)
源朝臣能有は、(以下のように)命ず。これまで取り締まりをしてこなかったのは国司の責任である。尾張、参河、遠江、駿河、近江、美濃、越前、加賀、能登、越中などの国に命じて特に厳しく取り締まり、このようなことを禁じる。もし強雇をしたなら、これを強盗に準じて処罰する。諸国は街道や船着場に高札を立て、今後このようなことがないようにせよ。
寛平6年(894年)7月16日
---------------------------------------------------------------
原文は類聚三代格巻19、禁制事、国史大系、類聚三代格後編・弘仁格抄p.624、吉川弘文館
(補足)
権勢家の使用人たちが強雇をした理由は、運送業が未発達の時代にあっては支配層の荘園からの年貢の輸送にも困難があったためである。それにしても、官に収める官物を道端に放り出すとは、いい度胸をしている。結局、政府の権威がなく朝廷の力が弱まっていた証拠であろう。

(3)平安時代後期の交換経済の仕組みと流通業者の役割
これまで、平安時代中期における物資の流通の仕組みについて述べてきたが、物々交換経済の中で、実際にどのような手順で取引が行われていたのだろうか。上総の前国司菅原孝標がここ大津・粟津でどのような取引をしたのか具体的に推測してみたい。
①菅原孝標の資産推定
孝標は上総に出発する時点で財産らしきものは持っていなかったので、全ては上総での稼ぎと考えられる。其の額はもちろん不明だが、一つの手がかりとして屋敷の購入費がある。孝標は粟津に到着後、すぐに三条上皇の御所三条第を購入している。下見、売買などがあったと思われるが寛仁4年12月2日(グレゴリオ暦1020年12月24日)に入居している。この邸宅は三条上皇の娘、禎子内親王に譲られた筈であったが、本人は幼児であり、実質的に後見人の藤原道長の所有であった。道長にしても上皇崩御後は空き家になっていたので処分してしまいたかった。そこに孝標がひょっこり上総から帰ってきたので、渡りに船とばかり売買の話が決まったのではないだろうか。価格は5000石、しかし上総帰りの孝標には買えたのである。ここから一体彼は上総でどの位の富を築いたか想像できる。因みにこの売買価格は正暦元年(990年)に三条坊門小路と東洞院大路に接する寝殿造りの屋敷が売買された時の価格だという。この場所は、まさしく孝標が購入した三条第か、三条坊門小路を挟んだ南側である。三条第だとすれば、一品宮資子内親王邸の可能性が高い(山口博:日本人の給与明細(Kindle版)、p.66、角川ソフィア文庫、残念ながら出典記載なし)。しかし、その辺の屋敷はこの位の価格(山口氏の試算によれば1.6億円)であることは間違いない。
大国の国司を一度務めても、次にいつ国司に任ぜられるか見通しはなく、全財産の半分以上を注ぎ込む事は考えられない。常識的な線として住宅購入費に25%を使ったと仮定すれば、菅原孝標の総資産は2万石とみてもいいのではないだろうか。現代価格に換算すれば6.4億円。千葉県知事を1期務めただけでこの報酬なら羨ましい限りである。但し、現代の米価を基に換算すると、古代とは生産性が全く異なるので価値を低く見積もりすぎる。平安時代ならもっと高額な実感があっただろう。
②菅原孝標、資産の使途(仮想試算)
仮に孝標が2万石の報酬を持ち帰ったとすれば、それはどういう財の形であったのが問題である。恐らく、軽貨といえども絹や布では旅の経費になる程度しか持ち出せないので、大半は上総国衙発行の切下し文(切符)になるしかない。幸い、国司(上総介)は自分なので、雑掌(出納係)に指示して作成させるだけである。その際、一枚で2万石ではなく、千石、二千石等小分けして複数枚で発行したのではないだろうか。“切符”の書式では米が名目でも実際に受け取るものが布であれば、その仕様と数量が明記されていなければならない。現代の有価証券とは別物なのである。上総国は都から遠国であり、米の上進はないため上総国大津納所には特産の布類の他、延喜式に定められた特産品しか輸送されていない。そこで面倒だが、上総納所で布を下付してもらい、それを民間倉庫業者に持ち込み必要な物品と交換する。或いは、布の現物を持ち込むのが面倒なら、例えば絹が必要な場合、上総納所の預り(支配人)に絹産地の国の大津納所宛てに切符を書いてもらうこともできたかもしれない。
表.2 資産の使途及び実際価値への変換
| 費目 | 価額(石) | 支払先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 (2万石) |
不動産(三条第) | 5000 | 摂関家政所 | 上総納所宛て切符を受け取ってもらえたか? |
| 投資 | 2000 | 上級貴族 | 付け届け(絹、馬等) |
|
| 500 | 定義教育費 | 文章生試験対策(布、絹) | ||
| 生活費 | 7500 | 米、大豆、塩、油、調度家具類、衣類、日用品 | ||
| 人件費 | 1000 | 使用人 | 布・手作布、米、衣類 | |
| 予備費 | 4000 | 倉に貯蓄 | 絹、布、衣類等現物 |
補足
・不動産の取得費として支払われた”米”5000石と表示された切符が上総納所に持ち込まれたら、納所は額面通り米を調達して渡さねばならない。もしそれと見合う布等で代替できるなら少し簡単になるが歴史的にどうだったか?。
・投資:現代なら株を買ったり預金、事業を始めて将来の収入を図るが、それがない時代には、再度、受領に任命してもらうために影響力のある貴族に日頃から付け届けをして覚えを良くしておかねばならない。跡継ぎの定義は文章生を目指していたと思われるが、田舎暮らしで十分勉強できなかったので、いい漢学者について勉強する必要があった。
・人件費:大きな屋敷に住めば、それなりに対面を保つため奉公人を雇わねばならない。食い扶持だけでなく、衣類も支給しなければならない。
・予備費:帰京後の定収入はわずかな位禄・季禄だけとなるので、ある程度貯えを手元に置いておく必要がある。そのためには保存性のある布・絹の反物が屋敷の中に貯えられた。
・実際に布を必要な場合は、布を請求する切符を作成してくれば、即、入手できた。細々したものは布を代価に民間倉庫で購入し、運送業者も手配してもらい三条の屋敷に届けてもらう。その時の代価も布で払う。
[感想]
平安時代に切下し文(切符)が、そのまま後世の手形、為替のように第三者に譲渡可能で流通できれば取引は相当円滑に進んだはずだが、その実例となる文書は発見されていない。おそらく、必要性は痛感されていただろうが、まだ実現してはいなかった。思うに当時の政府、社会には”信用”という概念や”担保”システムが育っていなかったということに尽きるだろう。有価証券の発生は鎌倉時代まで待たなければならなかった。平安時代の交換スキーム例としては
布を請求する切符-→上総納所、布を下付ー→布を持って民間倉庫で所望のものを購入ー→納品