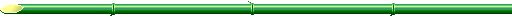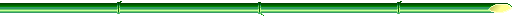-

更級日記に登場する多胡の浦(たごのうら)とはどこか
-

岫崎(くきざき)あるいは薩埵(さった)越え
-

駿河国における東海道、大井川の渡河コースは三度変わった
-
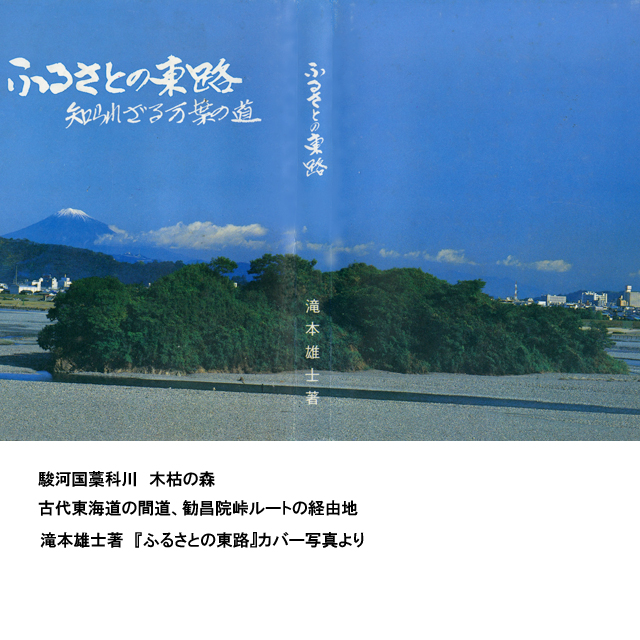
駿河国中部(安倍川西岸、丸子地域)の地誌と古代東海道、鎌倉街道
-
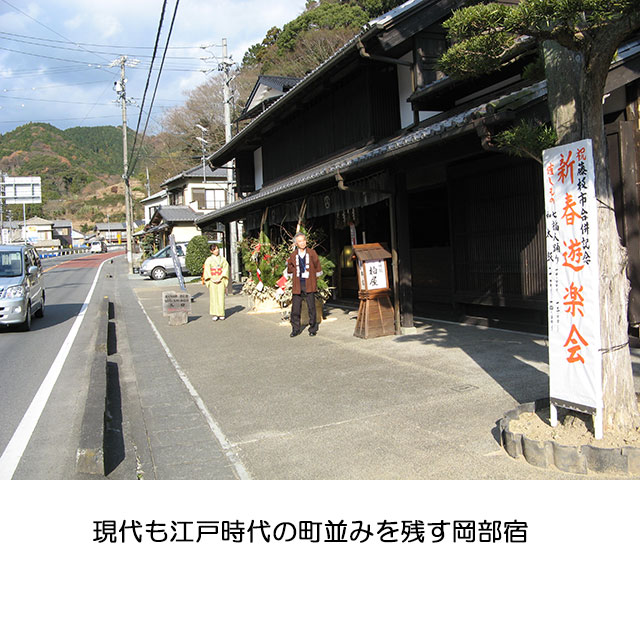
平安時代東海道における駿河国府の西よりの宿営地は岡部か
-
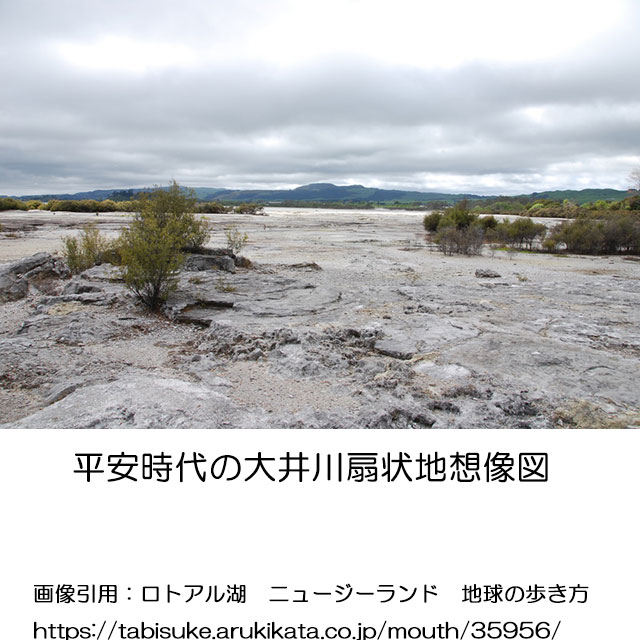
更級日記に記された駿河国最後の経過地『ぬまじり(沼尻)』の景観と現在地
-
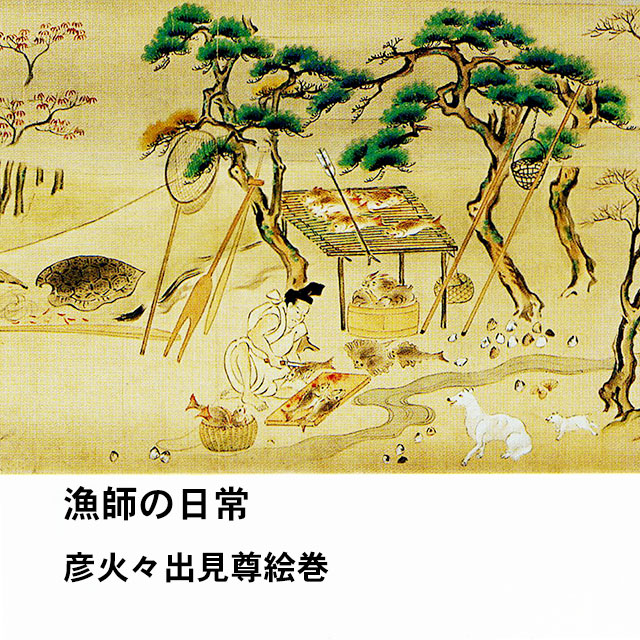
平安時代における海辺の集落の風景-宇津保物語に見る
-
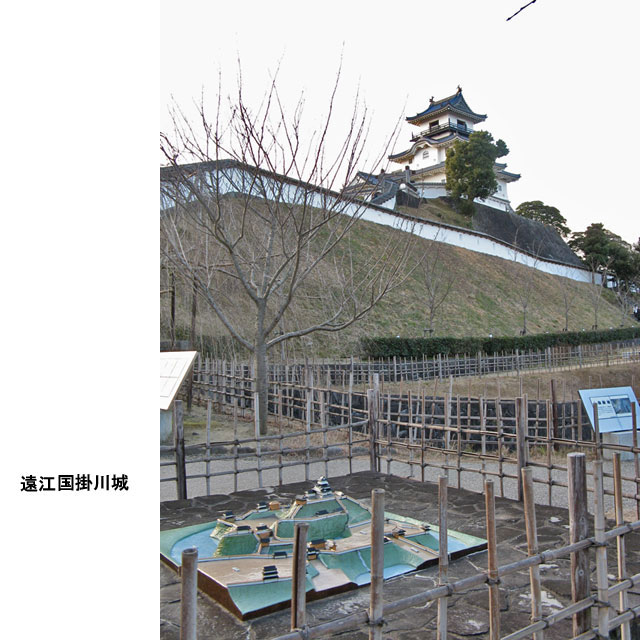
遠江国の駅家ー横尾駅について
-
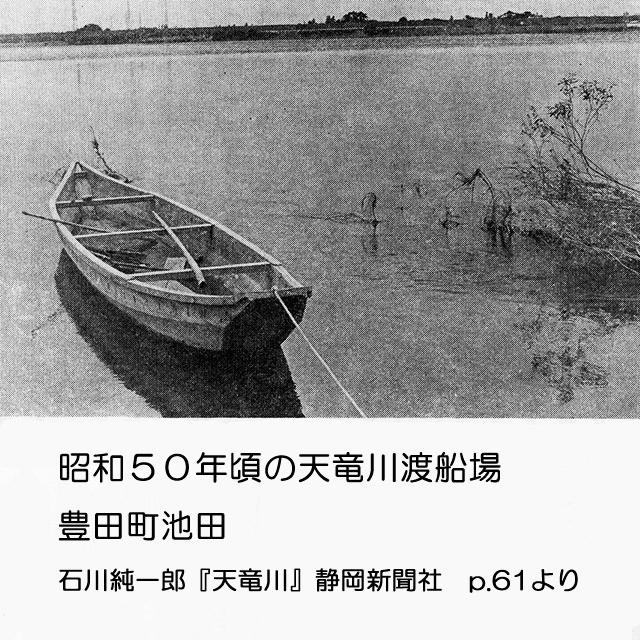
更級日記一行は天竜川河畔のどこで宿営したのか
-
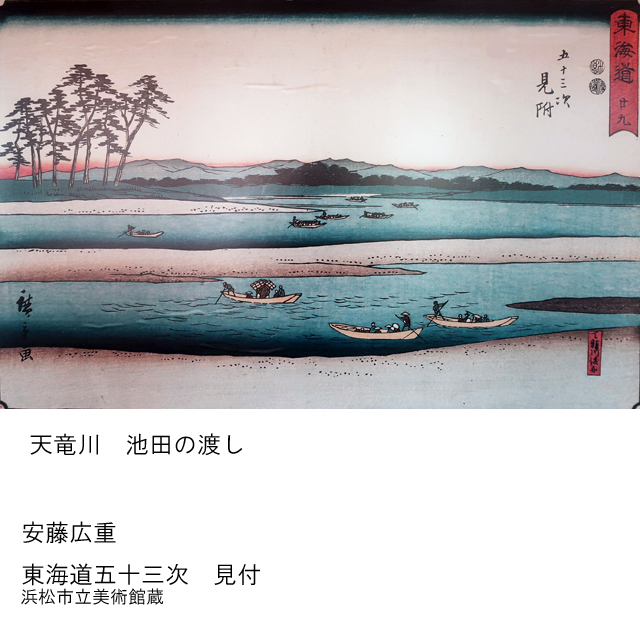
天竜川池田の渡しについて
-
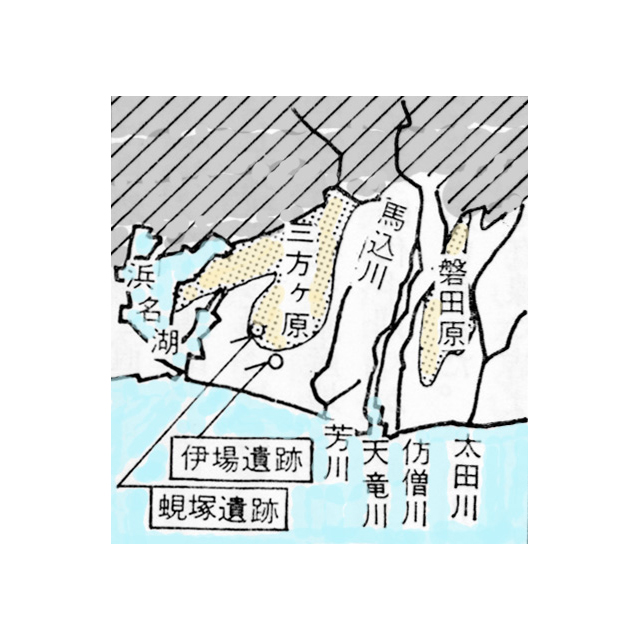
天竜川による遠州平野と、その海岸地形および浜名湖の形成
-
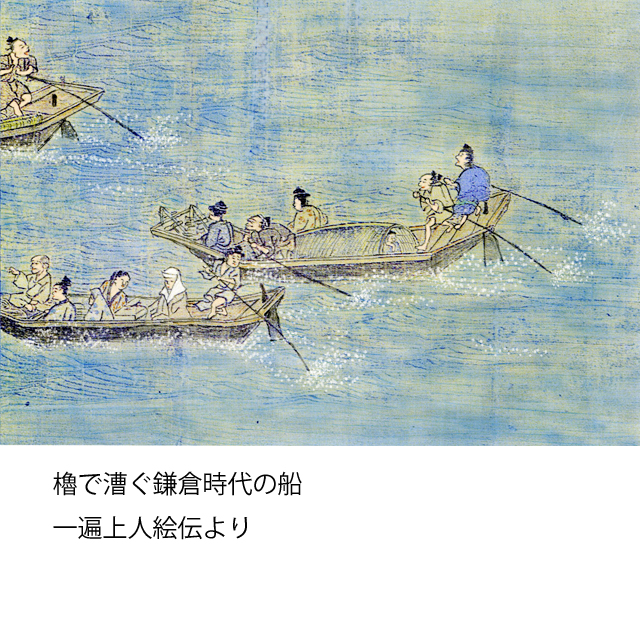
鎌倉時代の『海道記』によれば橋下から浜松の浦へは船便もあった
-
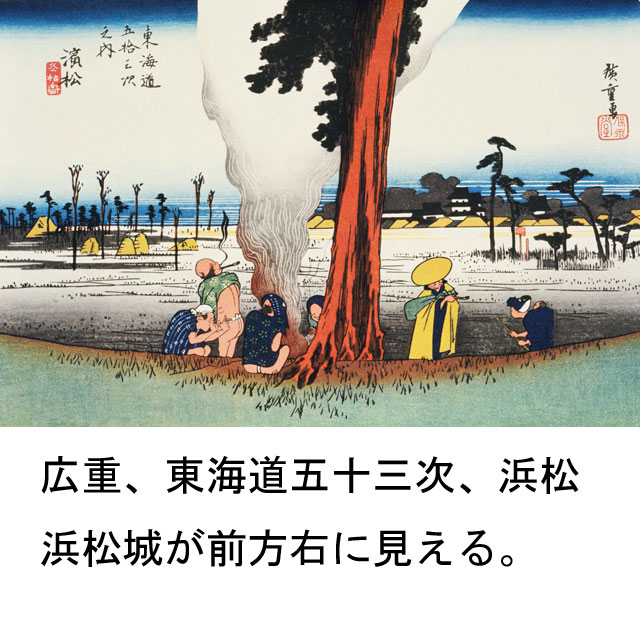
浜松周辺の平安時代東海道・鎌倉街道
-
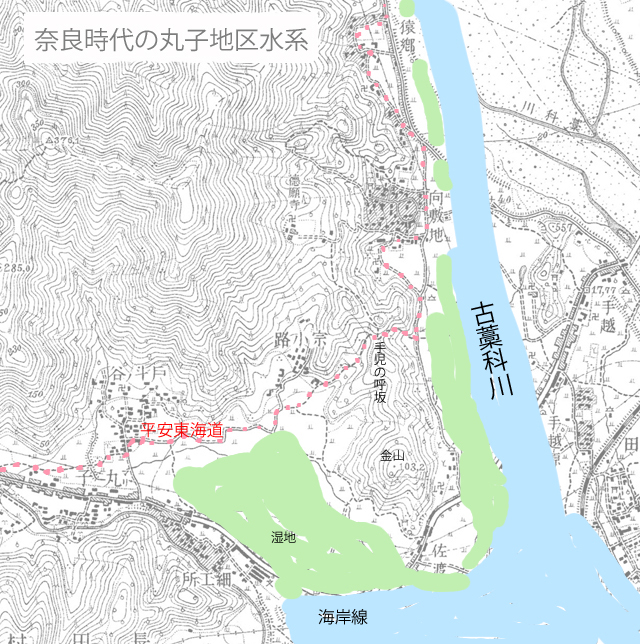
丸子・手児の呼坂の現地案内
-
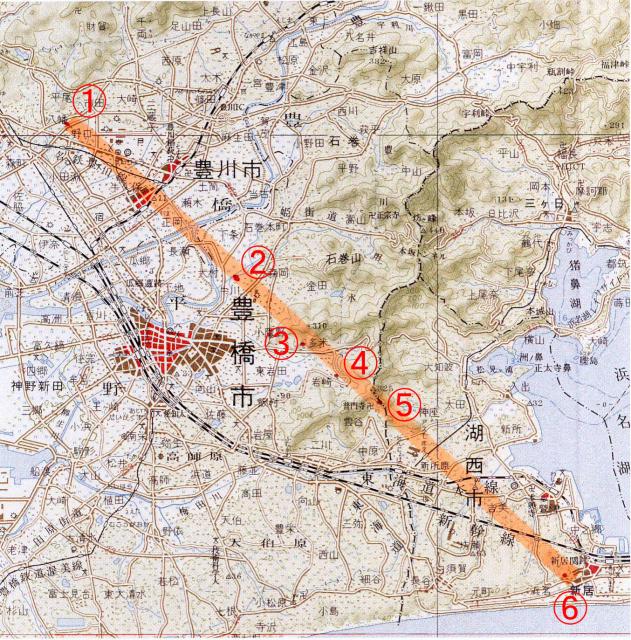
浜名から三河国府までの鎌倉街道
-

遠江国、大井川から天竜川までの平安時代東海道(鎌倉街道)
-
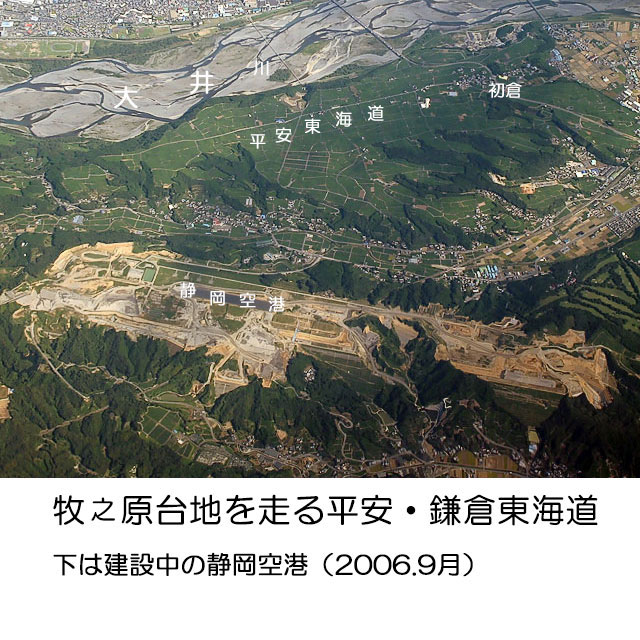
宇津の谷越えで遠江に入る平安時代東海道・鎌倉街道(岡部から菊川まで)
-

高師の山はどこか
-
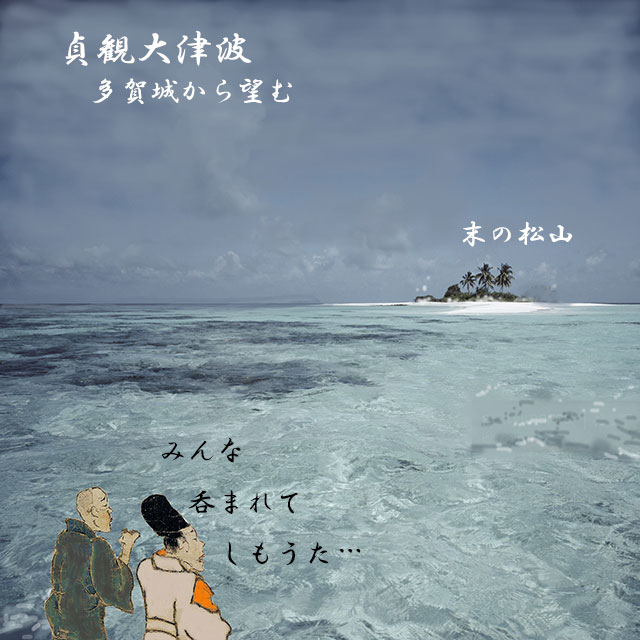
平安貴族の記憶に残る『末の松山』から貞観大地震・津波(1156年前の東北大震災・津波)の惨禍を辿る
-
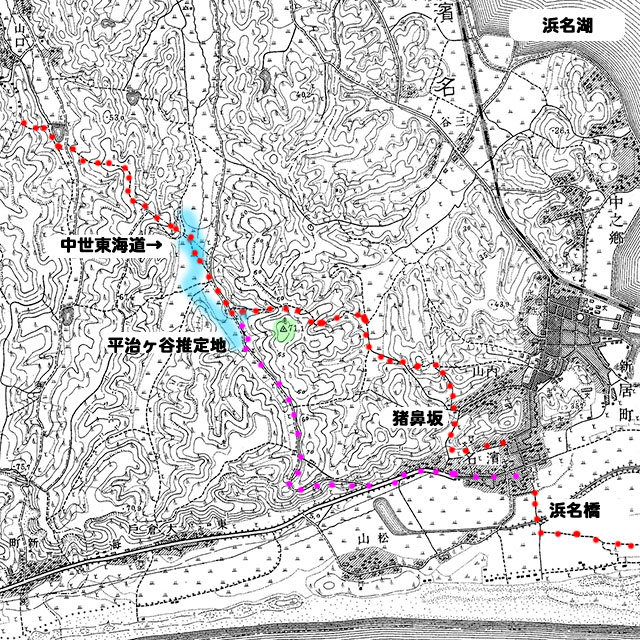
湖西市新居町にある平次ヶ谷(へいじがや)の歴史地理的意味